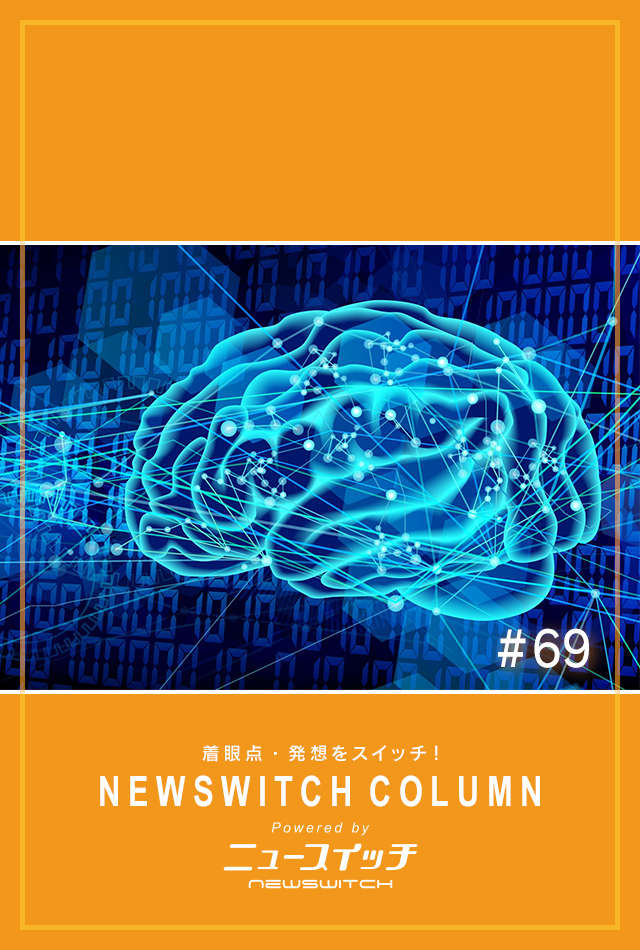SERENDIP編集部が厳選した書籍を紹介します。
毎年1月に米ラスベガスで開催されるテクノロジー見本市CESは、今年も、AIやVR(仮想現実)・AR(拡張現実)、半導体、量子コンピューティングなどの最先端技術が目白押しだった。
「特異点」シンギュラリティで何が起こるのか?
2010年代には、CESに「家電見本市」という日本語をあてるのが一般的だったと記憶しているのだが、技術とトレンドの変化のスピードは加速し、いまや「家電」の枠を超えてしまった。20年後の「2045年」には、どうなっているだろう。
数学や物理学の用語で、他と同じようなルールが適用できなくなる「特異点」のことを「シンギュラリティ」と呼ぶ。Googleの主任研究員兼AIビジョナリーで、世界屈指の発明家・未来学者のレイ・カーツワイル氏は、人間とAIが融合し、人間が本来の数百万倍の計算能力を有するようになり、人間の知能と意識が想像もつかないほど拡張されるようになる時点のことを隠喩的に「シンギュラリティ」と呼んだ。
20年前、2005年に刊行された『ポスト・ヒューマン誕生』(NHK出版、電子版改題『シンギュラリティは近い』)において、その特異点が「2045年」に起こると予測したのである。その後、「シンギュラリティ」という語がAIの未来を語る際に頻繁に用いられるようになったのは、ご存じの通りだ。
カーツワイル氏は、シンギュラリティに到達した後の世界は、「現在の人間の知能では」理解できないというのだが、氏の最新作で、『ポスト・ヒューマン誕生』の続編にあたる『シンギュラリティはより近く』(NHK出版)を読むと、それを想像してみることはできそうだ。
なお、変化が進むにつれて人間の認知能力は増強されるので、シンギュラリティにも対応できるようになるらしい。
脳とコンピュータが結ばれ、知能や意識が拡張される
カーツワイル氏によれば、2030年代には、自己改良型AIと成熟したナノテクノロジーによって、人間と機械はかつてないほど「結合」する。BCI(ブレイン・コンピュータ・インターフェイス)は極小化が進む。血流を通じて脳に入ったナノロボットが大脳新皮質の上の層とクラウドコンピュータを接続し、脳のニューロンとオンライン上にあるシミュレートされたニューロンを直接結ぶようになる。
その結果、いわばクラウド上に大脳新皮質が追加され、私たちはより複雑で抽象的に考える能力を持てるようになる。それがどういう状態なのか想像するのは難しいが、例えば「10次元の形を直感ではっきりとイメージして、理論づけができる」ようになるとか。SFの世界だと思うだろうか? しかし考えてみれば、30年前にはスマートフォンもSFだった。
SFといえば、カーツワイル氏が予測する、故人をデータからよみがえらせる「アフターライフ」も印象的だ。見た目、言動、記憶、スキルが故人にそっくりなAIアバターである。
似た例はすでにある。昨年、パナソニックとPHP研究所が、東京大学大学院の松尾豊教授が技術顧問を務める松尾研究所と共同で、生成AI技術を活用した「松下幸之助」再現AIを開発したというニュースがあった。今後は、「幸之助ならどのような経営判断を行うのか」など、経営面での示唆を提供できる人物再現AIを目指すとしている。
ただし、一般人のアフターライフへのニーズは、切実な個人的感情と結びついたものであることが予想できる。それが実現した時、私たちは受け入れることができるだろうか?
平野啓一郎氏の小説『本心』(文藝春秋)では、亡くした最愛の母のVF(ヴァーチャル・フィギュア、カーツワイル氏のいうアフターライフ)を作った主人公が、初めてVFの母に話しかけられた際、その場に崩れ落ちて涙する。一方で、その母に体がない故に、「触れない」ことで実在すると思い込もうとする様子もある。
カーツワイル氏は、2030年代後半には、ナノテクノロジーによってアフターライフがリアルな「肉体」をもつことも可能になると予測する。あと十数年後の話だ。人間の感覚や気持ちは、これに適応していけるだろうか。
危険もあるが「慎重な楽観論」でいるべき
カーツワイル氏の予測する未来は、容易には信じがたい世界だ。3Dプリンターの技術で患者のDNAを持つ移植臓器をつくったり、建物をモジュール構造でプリントしたり。老化の治療や寿命の延長が可能になり、暦が1年過ぎるごとに余命が1年以上延びる、つまり「寿命から脱出できる速度」に到達する――。驚くのは、ディストピアにもなりかねないように思える未来について、カーツワイル氏がかなり楽観的なことだ。
AIやBCI、ナノロボットなどの技術は悪用されると、とてつもないリスクが考えられる。アフターライフの権利など、倫理的、哲学的な課題も多い。それでも、全体として私たちは「慎重な楽観論」でいるべきだと、カーツワイル氏は述べるのだ。
考えていると頭が混乱してくるのだが、読みながらハッとしたことがある。仮に今、AIの開発をストップすれば、多くの命を救うことになる薬の開発が遅れるかもしれない、ということだ。AI開発は、進めることによって生じるリスクがある一方、止めることによって失われる未来もある。であるならば、カーツワイル氏の言う通り、「慎重な楽観論」を持って進めていくことが、現代人の責任なのではないか……?
個人的には、目の前の技術を追いかけるだけでも必死なので、生身の脳にカーツワイル氏の論は負荷が高い。それでもそんな未来が近づいているというのだから、少しでも学び、頭を柔らかくして、心の準備をしておきたい。
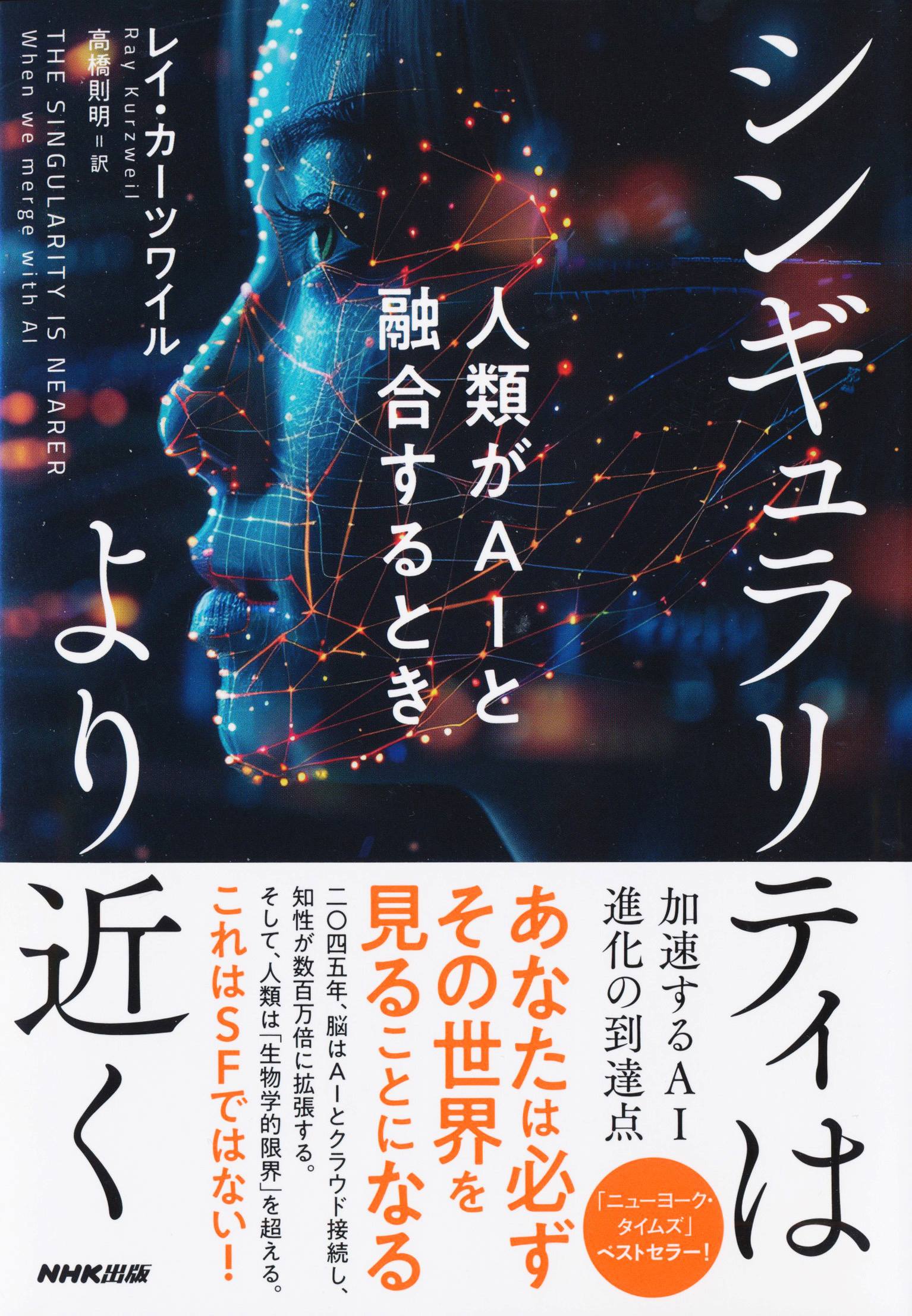
『シンギュラリティはより近く』
レイ・カーツワイル 著
高橋 則明 訳
NHK出版
448p 2,640円(税込)
文=情報工場「SERENDIP」編集部 前田真織
記者の目
レイ・カーツワイル氏の新作である本書は、2005年に「シンギュラリティは2045年」と予測したのを踏まえた、ちょうど中間時点に刊行された。時々背筋が寒くなるような未来技術を、誇張なく、こともなげに書き綴っているのが印象的だ。死者を蘇らせたり、「自分」の脳をコピーした分身が意識を持って行動するといった予測からは「どれだけ社会が混乱するか」といった懸念しか浮かばない。明らかにこれまで哲学で論じられてきた人間観、死生観などが根本からくつがえされるからだ。おそらく2045年を境にガラリと変わるのではなく、これから徐々に変化が進み「気がついたらすべてが変わっていた」というようになるのだろう。社会意識とテクノロジーのズレが最小限になればいいのだが。(吉川清史 情報工場 チーフエディター)