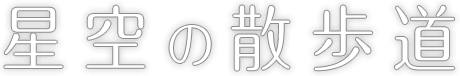Vol.125
重力波で捉えた中性子星合体の現場
2017年のノーベル物理学賞は、重力波の検出に貢献のあった研究者に贈られたのは、まだ記憶に新しいだろう。重力波の直接検出が大々的に報じられたのは2016年2月。アメリカで試験運用に入っていたLIGO(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)は、リビングストンとハンフォードと、国内に離れて二カ所に設置された観測装置である。4kmもの腕の長さを持つレーザー干渉計が、物理学の長年の夢だった重力波を直接捉えたのだった。記者会見当日、私もわくわくして深夜のインターネット中継を眺めていた。多くの記者が世界中から集まる中、ついに人類初の重力波の検出が報告された。
「We did it!」
責任者が、この言葉を発すると、記者からは拍手が鳴り止まず、私も深夜の自室で大きな拍手をしたのを覚えている。新聞社からコメントが求められていたこともあり、発表内容を聞き逃すまいと、画面に集中していたが、理論の予測通りの見事な信号のグラフに、思わず「すごい」と叫んでしまったほどだった。検出された重力波の解析から、約13億光年の彼方で、太陽質量の29倍と36倍のブラックホール同士が合体したという。太陽3個分の質量が重力波のエネルギーとなって、その一部がはるばる地球に届いたのである。この歴史的検出から、わずか2年にも満たないノーベル賞受賞である。それほど成果に関する高い評価は揺るぎないものだったといえるだろう。
歴史的な瞬間に立ち会い、その夜は興奮でなかなか寝付けなかったほどだが、一方で天文学者からすると物足りなさも感じていた。最初の検出では、重力波源の方向が特定されなかったからだ。リビングストンではハンフォードに比べて7ミリ秒ほど早く信号が来ていたので、南天の現象らしいことはわかったのだが、あまりに範囲が広すぎ、天体望遠鏡を向けて重力波源を探すのは困難だった。欧州の重力波検出装置VIRGOや日本のKAGRAが稼働すれば、この方向がかなり特定され、本当の意味での「天文学」になるはずだ。
そして、その時は意外に早くやってきた。ノーベル賞受賞にわいた約2週間後、日本を含め、世界中で一斉に記者会見が開催された。欧州のVIRGOが重力波の検出戦線に加わり、今年の夏8月17日に新しい重力波を捉えたのだが、それまでとは異なる波形から、2つの中性子星が合体した際のものであることが明らかになった。驚くべき事は、それだけではなかった。VIRGOも検出したおかげで、その重力波源の方向が、かなり狭まったのである。こうして世界中の天体望遠鏡が、重力波源の捜索に血眼になった。重力波検出から約11時間後、複数の望遠鏡がこの重力波源に対応すると思われる光源を特定することに成功したのである。この天体は、1億3000万光年の距離にあるうみへび座の銀河NGC 4993にあった。こうして重力波源に対応する天体がはじめて可視光、赤外線などの電磁波で検出され、約70台の天体望遠鏡や天文衛星が数週間にわたって観測を行ったのである。もちろん、日本の重力波追跡観測チームもハワイにある国立天文台のすばる望遠鏡や南アフリカに設置された名古屋大学・鹿児島大学のIRSF望遠鏡、名古屋大学・大阪大学が運営するニュージーランドの望遠鏡群を動員し、その明るさが減光していく様子を捉えることに成功した。その結果、理論的に予測されていたキロノバ(kilonova)と呼ばれる現象に酷似しており、中性子星合体に伴う現象で鉄より重い元素がかなり大量に合成されていることも判明した。理論計算には国立天文台のスーパーコンピューター「アテルイ」も活用された。金や白金などの元素は、通常の超新星爆発では、それほど作られないと考えられており、今回の成果は宇宙の元素合成解明に一石を投じることにもなったのである。

今後、日本のKAGRAが検出戦線に加われば、さらにさまざまな重力波源が見えてきて、様々な発見が続くと思われる。文字通り、重力波天文学の萌芽期、新しい時代の幕開けである。