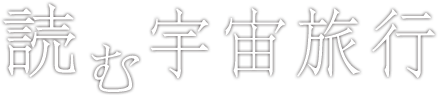MOMO4号機年内打ち上げへ!
日本初民間ロケット成功の要因と戦略
ついにこの日がやってきた。5月4日(土)5時45分、北海道大樹町から打ち上げられたMOMO3号機が高度113.4kmに到達。日本初の民間宇宙ロケットが誕生したのだ。

「成功すれば流れが変わると思っていましたが、予想以上でした」と語るのはMOMOの開発、製造、打上げを実施したインターステラテクノロジズ(IST)社の稲川貴大社長だ。打ち上げ成功後、文部科学大臣や内閣府の宇宙政策担当大臣がコメント。今まで同社のロケットを取り上げたことがなかった大手経済新聞が社説で今回の打ち上げ成功にふれ、「(国による)小型ロケット事業の育成を」と書いたことにも驚かされた。
「今回のMOMO打ち上げ成功で、(今後、同社が目指す本丸である)超小型衛星打ち上げ用ロケットについても様々な実証ができた。MOMOを拡大すれば大丈夫という自信になった」と稲川社長は語りつつ、さっそく次の打ち上げに向けて、気を引き締めている。
「ロケットは成功率で語られる。一回うまくいったからといってその後100%うまくいくわけではない世界。物づくりはもちろん、(連続打ち上げに向けた)体制や品質管理を構築し、エンジニアの熟練度をあげて続けて成功して初めて、ビジネスが成り立つ。具体的にはMOMO4号機を年内に打ち上げようと思っています」
稲川社長によると、MOMO3号機までは実験という位置づけだった。4号機からはいよいよ商業化に乗り出す。つまり、お客さんの荷物を載せて打ち上げることになる。4号機は3号機までとは大きな設計変更はせず、打ち上げを再現させ、成功率を上げることを目指すという。

2号機失敗のショックから、3号機打ち上げ成功へ。成功の要因は?
MOMOの商業化について詳しく書く前に、今回の打ち上げ成功の要因をふり返っておきたい。MOMO初号機は2017年7月30日打ち上げ。発射約66秒後に通信途絶。空気の力を最大に受ける「マックスQ」と呼ばれるタイミングで機体が壊れたとみられる。対策を施して挑んだ2号機は2018年6月30日打ち上げ。発射4秒後にエンジンが停止し落下、炎上。事故の衝撃的な映像はSNSで瞬く間に拡散された。
「2号機失敗は衝撃でした。もう少し高く上がってマックスQを超えていれば、ショッキングな映像ではなかったという想いもあります。でも不幸中の幸いがいくつかあった。ロケットのお尻から落下したために(酸化剤の)液体酸素が漏れて周りのものは炎上しましたが、燃料はほとんど漏れなかった。つまり爆発ではなかったのです。おかげで設備も機体もかなり残っていて、原因究明が速やかにできました」(稲川社長)。もし爆発していたら、3号機打ち上げはもっと遅れる可能性があったという。
2号機の失敗後、ISTのエンジニアたちは落胆したかと思いきや「燃えた」という。「洗いざらい全部見直して『あれを良くしよう』、『これも良くしよう』と改善点がいっぱい出てきて、クオリティや生産性が上がりました」。
稲川社長がMOMO3号機成功の最大の要因とあげるのが、今回初めて実施したエンジン燃焼試験CFTだ。ロケットの実機を飛翔できる状態で地上に固定して、実際の飛行と同じ120秒間のエンジン燃焼実験を2回実施した。打ち上げと同じぐらい費用がかかる高価な試験だ。これまで同社はロケット発射を実験ととらえ、地上で高価な試験を繰り返すよりも実際に打ち上げて問題を洗い出そうと考えていた。しかし2号機の失敗原因を考えた時、「CFTをやっていれば事前に防げたことだよね」と社内で議論。トラブルを打ち上げ前に抽出するためにCFT試験実施に踏み切ったのだ。
さらに元JAXAやMHIで日本のロケット開発を率いてきた、エキスパート(ロケット野郎)たちによる外部原因対策委員会も設立。北海道大樹町の開発現場を見てもらい様々な助言を受けたという。こうしてロケット自体のクオリティもあがり、エンジニアも育っていった。MOMO3号機打ち上げ本番は当初4月30日に予定されたが、新しく採用した部品にトラブル発生。原因を即座に究明するとともに確認試験を行って、打ち上げ可能期間内で成功にこぎつけた。これらトラブルシュートがうまくいったことも、チームの成長の証だ。
MOMOパワーアップ、もっと高く or 回収可能に
ISTは年内にMOMO4号機打ち上げを成功させた後、少しずつMOMOの能力を上げる計画だ。「軽量化とエンジンの改良によって、もっと高い高度に上げるか、重い荷物を運ぶことができるようにしたい」(稲川社長)
観測ロケットMOMOの商業利用を進めるため、ISTは様々なニーズをクライアントからヒアリングしている。高度200kmあたりを観測したいという需要や、もっと重い荷物を打ち上げたい(現状約20kg)、さらに打ち上げた荷物を回収したいというニーズもあるという。MOMO3号機は打ち上げた荷物は回収せずロケットごと海底に落下させたが、分離機構をつければ、荷物だけを回収できるようになる。
たとえばMOMO3号機には相模原名物「とろけるハンバーグ」が搭載されたが、回収できなかった。もし回収できていれば「宇宙を飛んだハンバーグ」の変化が、さらに注目を集めたはずだ。ISTファウンダーの堀江貴文氏は「ともすると『くだらない』と思えることに利用されてこそ、宇宙産業は大きくなる。インターネット黎明期もそうだった」と語る。確かにネット黎明期には、今のように社会のあらゆる場面でネットが活用される未来は予想できなかった。
宇宙利用の様々なアイデアを気軽に試すために大事なのが打ち上げコスト。安ければ、何かやってみようという気になる。MOMO打ち上げ費用は数千万円。ライバルは?「今のところ国内にはありませんが、JAXAの観測ロケットの打ち上げ費用は2~5億円と言われています。我々は一桁安い」(稲川社長)。
JAXAの観測ロケットは近年打ち上げが行われていないが、募集すれば多数の応募があるという。大学などの実験や観測が中心だが、「大学で科学研究費をとってもらうか、JAXAから(ISTが)観測ロケットの発注を受けるような枠組みができれば、大きな需要があると思っている」(同)
なぜ、MOMOは国のロケットより一桁安い打ち上げコストを実現できるのか。「社内で技術開発をしていること、高い部品や高い作り方を極力避けていること」を稲川社長は挙げた。コストを劇的に下げられるものの一つがエンジンで燃料を噴射するインジェクタと呼ばれる部品。MOMOはアポロ月着陸船で使われたピントル型の技術を応用した。「国の基幹ロケットでは大量の溶接があり品質保証された1000万以上かかる部品を採用しているが、ピントル型は汎用の工作機械で1~2日で作る。素材もステンレスや銅の汎用品を使い、部品点数も少なく、極めて低コストに作ることが可能」

宇宙専用のものをなるべく使っていないことも大きい。例えばジャイロセンサーはドローンに使われているような民生品の半導体ジャイロを使っている。国の基幹ロケットで採用されるジャイロより性能は劣るものの、コストは二桁安いという。民生品を活用しつつ、外注すると高くつくアビオニクス(電子部品)や推進剤タンクなどは社内で作る。一方で、燃焼試験などはお金をかけて実施する。抑えるところは抑えつつ、試験はしっかり行うことで低コストと信頼性を両立させた。
本丸は超小型衛星打ち上げロケットZERO開発

そしてISTが目指す本丸は、MOMOの先にある。超小型衛星打ち上げロケットZEROだ。現在、世界中で超小型衛星を打ち上げたいというニーズが急上昇している。アメリカの調査会社によると、今後5年間で2000機以上の超小型衛星(50kg以下)が打ち上げを待つとされる一方で、超小型衛星を打ち上げられるロケットは年30本程度。目的の場所に「安く」「早く」「確実に」届けてくれる小回りの効くロケットが、切実に求められているのだ。世界中で約100社(ISTもその一つ)がこのマーケットを狙い、ロケット開発を競っているが、現在打ち上げに成功しているのは米国の企業1社のみ。
ISTが衛星打ち上げロケットZEROを実現するために肝となるのは、エンジン。MOMOの5倍の推力が必要になる。エンジンに燃料を送る心臓部=ターボポンプを新規開発する必要があるが、JAXAが技術協力することになっており、強力な援軍となる。JAXAにとっても低コストロケット開発の知見が得られることになる。
「ZEROは大型になるがロケットの基本は変わらない。MOMOとZEROのかなりの部分は共通であり、MOMOで実証ができた。きちんと開発していけば、世界の超小型衛星用ロケット市場で十分に勝てると思っている」(稲川社長)
ZEROの打ち上げは2023年を目標に掲げる。ロケット開発と同時に、北海道大樹町の発射場にZEROを打ち上げるための射点を整備しなければならない。発射場整備の資金調達のために、ISTは発射場のネーミングライツ(2年間)を5400万円で販売中だ。公式の呼び名やグーグルマップにも掲載されるという。これも宇宙業界では初の面白い取り組みだ。
宇宙という舞台で多彩な活動を展開するには、舞台で活躍する「役者=衛星」を届ける「運び屋=ロケット」が欠かせない。新しい時代、令和の始まりと共に飛び立った全長9.9mのミニロケットが、今後の宇宙開発を大きく変えるかもしれない。地道に泥臭く、同時に高い目標に向かって楽しみながらロケット開発にまい進する彼らの今後に期待し、応援したい。

- ※
本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。