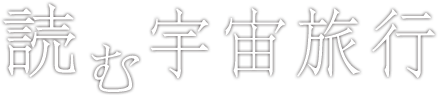「この指を離せば宇宙の藻屑に」—野口飛行士が語る極限の船外活動

宇宙、深海、8000m峰・・極限環境に置かれると人間の身体や感覚は変化(進化)し、新しい能力を獲得していくようだ。極限に挑む人たちの話はゾクゾクするほど面白い。
例えば水深100m付近の「グラン・ブルー」の世界に素潜りで潜るフリーダイバーの篠宮龍三さんは、グラン・ブルーについて「神聖で美しい青」でありその世界に入ると「光も音も重力も感じない闇に近い。宇宙だと感じる」と表現する。だが宇宙と海で決定的に異なるのは体に襲いかかる水圧だ。110m付近で約12気圧にもなる水圧に耐えるため、篠原さんはヨガで鍛えた横隔膜で肺を持ち上げて小さくし、肺内部の圧力を高める。雑念を捨て海と自分を調和させることに成功すると、「母なる海に抱かれるような」至福のひと時が訪れるという。「ゾーン状態に入り、スローモーションのように物事がゆっくり進んで見える」。篠宮さんはその独特の感覚を表現した。
高い頂きを目指す登山家はどうか。地球上にある8000m峰14座のうち11座を無酸素で登頂した竹内洋岳さんは、山頂に近づくほど脳の処理スピードが落ちる一方、全身の感覚が鋭敏になるのを感じると言った。匂いや音、振動などのごく僅かな変化から雪崩の危険を察知する。「指先はもちろんアイゼンの刃先まで神経が届いている気がする」と。夜中にキャンプから山頂に向かって歩く時、ヘッドトーチが照らす範囲2~3mの先は闇。「方向感覚が失われ、山頂に向かうというより、深い海に潜るよう」。7900m付近の超高所でビバークし20時間以上も無酸素で過ごしたときは「太古の地球の薄い酸素、低気圧を生き延びた生命の能力が、自分の中で呼び起こされ再起動する感覚を得た」と語ってくれた(欄外リンク参照)。
海で宇宙を感じ、山で深海を感じる人間の感覚の面白さ、不思議さ。さらに興味深いのは極限環境に置かれた人間が新しい身体能力を獲得していることである。竹内さんは登山後の血液検査では毎回、酸素の運搬料を増やすヘモグロビンが増えるという。人間はまだまだ進化できる。彼らの話を聞きながらそう感じていた。
極限環境の代表格、「宇宙」で人間はどんな感覚を得るのだろうか?
宇宙の夜—腰から下がなくなったとしてもわからない!

宇宙飛行士が得る身体感覚について、最も興味深いのは船外活動時ではないだろうか。ISS(国際宇宙ステーション)の中は無重力環境ではあるものの、空気が満たされ温度や湿度が一定に保たれている。だが船外活動では、「ミニ地球」であるISSの外に出る。宇宙服を隔てた外側は生き物の存在を許さない「死の世界」だ。万が一、小さなゴミがぶつかってヘルメットにひびが入ったり、ISSの構造に宇宙服をひっかけて小さなほつれができたりすれば、宇宙服内の空気が漏れ出し、命の危険にさらされる。
そして、ISSと自分をつなぐのは基本的にテザーと呼ばれる細い命綱1本。その命綱が切れれば、ISSから離れ、宇宙空間に一人放り出されてしまう。そうした緊急時に備えて、窒素ガスを噴射して移動するレスキュー用装置SAFERを宇宙服の背中部分に装備しているものの、2018年に船外活動を経験した金井宣茂宇宙飛行士は「両手を離して作業するとき、二度と帰ってこられないような、そんな怖さを感じた」と語っている。

さらにISSの飛行する高度約400km付近では、昼と夜が45分ごとに訪れる特有の昼夜サイクルにも順応しなければならない。昼と夜の変化について「真夏のビーチから急に洞窟に放り込まれるよう」と野口飛行士は表現する。昼間の温度は120度以上、夜はマイナス150度以下。対応するため準備が必要だ。昼間はヘルメットのサンバイザーをおろし、宇宙服内部の温度が上がりすぎないように冷却下着に水を回す。一方、夜が来る前にヘルメットのランプをつけ、指先が凍えないように手袋内のヒーターをオンに。これらの作業を宇宙服内外の気圧差でぱんぱんに膨れ上がった手袋で行う。
宇宙に放り出される恐怖、真空の宇宙で作業する緊張感、昼夜サイクルの混乱・・。宇宙船の中にいるのと外に出るのは全く異質の体験であり、船外活動は宇宙飛行士の誰もがやりたがる「花形」だと聞く。だが死と隣合わせの危険な作業でもあるのだ。

野口飛行士は2005年の初飛行で、3回の船外活動をリーダーとして主導した。その時の感覚を書籍(「宇宙に行くことは地球を知ること」野口飛行士、矢野顕子さんとの共著)でじっくりお聞きしたが、印象に残ったのは宇宙の夜の話。「自分の足が曲がっているかのびているのか、まったくわからなくなった」。極端な話、「腰から下がなくなってもわからない」。腕も同様であり「身体感覚が一気に分断したようでとまどった」と野口さんは語った。地上では目を閉じていても、足が曲がっているかのびているかわかる。それは筋肉が重力を感じていて、重力に抗って足を曲げ伸ばしすればその情報が脳に届くからだ。だが重力のない宇宙では筋肉からの情報は脳に届かない。さらに視界が限られる夜は、目で足の状態を確認できない。自分の姿勢や位置を見失い、ISSで迷子になることも起こりえると聞いた。
興味深いのは、視覚が十分に機能しなくなったときに他の感覚がそれを補うように働きだしたという話。例えば「指で感じる水平線」。幅約109mのISSを水平に貫くトラス、つまり橋げたが新たな「水平線」となる。トラスを手で伝って移動することで、たとえ目を閉じていても水平方向や垂直方向を認識し、「新しい秩序」を構築するようになる。さらに「(手袋の)硬さで感じる温度」「指先で聞く音」などあらゆる感覚が補い合う「感覚のクロスオーバー」が起こったという。
では、2021年3月頭、約7時間にわたって行われた船外活動はどうだったのか。
昼なのに暗い—光こそが自分の存在を確認する手立て

野口さんが今回船外活動を行ったのはISSのもっとも端。新型太陽電池パネルをとりつけるための土台の設置作業だった。
「15年前にも3回船外活動を行いましたが、その時はISSがまだ小さかったこともあり、(ISSの中心部で)ずっと作業を行いました。夜は暗くなり手元しか見えない感覚をよく覚えているが、それでもヘルメットから出た光がISSの何らかの構造物にあたって反射するから、頭を回せば(ヘルメットの)サーチライトが広がり、色々なものが見えて空間認識を構築していた」。5月末、宇宙から帰還後の野口飛行士の記者会見が行われた際、船外活動で得た感覚を聞いた。野口さんはまず前回の船外活動について説明して下さった。
今回は?「ISSの巨大なトラスという橋げたのような構造物の、一番端で作業をしました。しかもその橋げたの外側を回り込んだ。なかなか大変な作業でした」
ISS全体はサッカー場ほどの大きさがある巨大な構造物だ。宇宙飛行士が暮らす居住棟はサッカー場で言えば中央のハーフウェーラインあたりに集まっているが、今回野口飛行士が作業をしたのは、サッカー場のゴールポスト、さらにその外側だった。
「ちょうど(外側を)回り込んでいるときにふと気づいたら、真っ暗だった。瞬間的に夜だからしょうがないなと思ったが、その時『ついさっき日の出だったな』と思い出して。ふと足元を見たら、地球が煌々と照らされている。つまり太陽が出ている昼間だった」
大気のない宇宙では、昼間でもあたりは暗い。太陽の光はISSのモジュールや太陽電池パネルなど反射するものがあれば輝くが、構造物がなければかえってこない。真っ暗なままだという当たり前のことに気付く。
「橋げたの一番端っこで外側(宇宙の方)を向いてヘルメットのライトをつけても本当に何も見えない。真っ暗なままでした」。光が闇に吸い込まれていく。「その時点で自分と世界を繋ぐものは、トラスの端っこにある手すり一つだけ。手すりを掴む指を放したら、僕は宇宙の藻屑になって吸い込まれてしまう」。すぐ傍らに漆黒の闇、指を離したら宇宙の闇に引きずり込まれ、藻屑になるような恐怖と戦いながら行う7時間の作業。想像を絶するような緊張感の中で難易度の高い作業を成功に導いたとは、なんたる強靭な精神力。
会見で最も印象に残った野口飛行士の発言はその後の言葉だった。「光こそが自分の存在を確認する数少ない手段だと改めて認識しました」。光に照らされなければ、存在しても確認できない。光と闇、生と死、存在そのもの・・会見中のわずか数分の回答の中で様々なことを考えさせられた。野口さんはまだこの体験を整理しきれていないという。どんな感覚や進化(或いは深化?)が生じたのだろう。是非、言語化して私たちに共有してほしい。

- ※
本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。