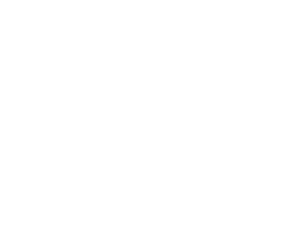工房訪問篇 染付窯屋「眞窯」
約1,000年の歴史を誇る瀬戸焼。その発祥地である愛知県瀬戸市周辺は、良質な陶土(特に木節粘土)が豊富に産出され、また窯の
燃料となる木材にも恵まれた土地で窯業が大きく発展しました。多様な釉薬(ゆうやく)や成形技術を柔軟に取り入れることで、茶碗、皿、
徳利、花瓶など、日常生活で使用される「瀬戸物」と呼ばれる陶磁器を数多く生み出してきました。


父、母、娘が紡ぎ出す
白と藍色の美しきコントラスト
瀬戸市の北東部、長閑な田園風景に囲まれた品野町にある「眞窯」は1919年創業の窯元。
100年以上にわたり、白と藍色のコントラストと文様が美しい瀬戸染付焼を手掛けています。四代目となる真雪さんは、三代目である父・眞也さんと母・美穂子さんの3人で伝統の技を礎としながら、生活を彩る様々な器や装飾品を制作しています。

瀬戸染付焼とは、白い磁器の素地に呉須(ごす)と呼ばれる焼くと藍色に発色する顔料で絵付けをする技法のこと。19世紀のはじめ、この地の陶工・加藤民吉が九州から磁器の焼成技術を取り入れ、19世紀中頃には瀬戸染付焼の基礎が確立されました。古くから分業体制が確立されており、採掘された土を精製して不純物を取り除く水簸(すいひ)屋、精製した土をブレンドする製土屋、型を使って製品を成形する型屋などの職人が各工程を担っています。


職人の息吹が宿る
「眞窯」の器づくり
では、「眞窯」での具体的な作業を見ていきましょう。
まずは製土屋から届いた土に水と薬剤を加えて撹拌(かくはん)し、器の型に流し込むのに適した粘度の泥しょうにします。次に、それを型に流し込みます。この型は石膏でできており、中に泥しょうを流し込むと石膏に触れる部分の水分が吸収され、固まっていく仕組みです。


季節によって固まる時間は変わりますが、理想の厚みに固まったところで型を逆さまにして排泥(はいでい)します。「ガバ鋳込み」とも言われるこの作業で余分な泥水を出すと、固まった部分だけが残り、型の中からマグカップが姿を現しました。この後は乾燥させて低温で素焼きを行います。最終的には型から出した時の約9割の大きさになるので、実際の商品の大きさから逆算して型の大きさを決めるそうです。
100年続く
白と藍色のコントラスト


呉須が織りなす
染付けの技巧と美学
素焼きを経て、瀬戸染付焼の肝とも言える染付け工程になります。美しい藍色の元になるのは、呉須という酸化コバルトを主原料とした顔料。お皿には判子で押された下絵があり、鉛筆で線をなぞることで線の部分は呉須をはじき、焼き上げると鉛筆の部分が焼き切れ、白く抜けます。

早速、加藤さんにお皿の染付け作業を行っていただきました。大きく太い筆を使い、絵の具をスポイトのように流し込んで描く“濃み(だみ)”と呼ばれる染付け特有の技法で濃淡をつけていきます。これは素焼きが水分を吸う性質を利用したもので、紙や布ではできない技法です。筆に使われる毛は蝦夷鹿の冬毛で、1本1本が極細のストロー状となっているため、筆の傾きだけで絵の具を出すことも戻すこともできるそうです。
「筆先をつけずに、表面張力で盛り上がっているところを引っ張って動かしていきます。濃淡は器に吸わせる量でつけていきます」(加藤さん)
染付け後は基本、釉薬(ゆうやく)をかけて「ねらし」という瀬戸地方独特の焼成を行います。高温で一定時間温度を保ちながら焼くことで、呉須は潤いをもった美しい藍色へと変化します。

この日、加藤さんと対談する三菱電機・澤部健司も染付け作業を体験させていただきました。
「筆で色を置いてお皿の角度を調整しながら濃淡をつけるのは、とても繊細で難しかったです。まさに手仕事の原点とも言える体験でした」(澤部)
「染付けの技術の中でも、1番難しいと言われているところなので。でも、普段から手を動かしている人は、やはり飲み込みが早いですね」(加藤さん)





工房を離れた一行は隣接するギャラリーへ場所を移し、加藤さんと澤部の対談を開催。2人のものづくりに込めた思いを語り合っていただきました。
- 取材・文/澤村泰之 撮影/魚本勝之
- 2024.10.09