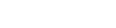Vol.1
アストロバイオロジーという視座
アストロバイオロジーとは
どうして僕にたどり着いたのであろうか。大学の一研究者でしかない僕の元にも、ときに高校生や中学生からメールが届く。
内容は、宇宙、とりわけ宇宙における生命に関する質問がほとんどである。どんな疑問にも答えてきたつもりだが、たいていメールの最後は以下のような質問で締められており、僕はいつもこれへの返答に困るのである。
“アストロバイオロジーを学ぶには、大学で何学科に行くのがよいでしょうか?”
アストロバイオロジーという言葉を、初めて目にした方もおられるかもしれない。アストロは“宇宙”、バイオロジーは“生物学”と訳される。すなわち、アストロバイオロジーを文字通り訳せば、宇宙における生命に関する学問という壮大なテーマとなる。言い換えれば、“生命はどのように誕生・進化してきたのか、この宇宙に我々以外の生命はいるのか”という、誰もが一度は考えるであろう素朴だが根源的な疑問に答えようとするものである。
実は現在、地球外生命の発見前夜といってよい状況にある。火星では、かつて湖の底だった泥の上を今日も探査車が走り回り、生命の痕跡を探している。木星や土星の月では、氷の地面の下にある地下海から海水が宇宙に噴き出しており、探査機がその海水をキャッチして、成分を調べている。また、太陽系の外に目を向ければ、無数に存在する太陽のような星の周りにも多くの惑星が見つかっている。系外惑星と呼ばれるこれら惑星の発見は、もはや珍しいことではない。第2、第3の地球と呼ぶべき、地球に似たサイズの系外惑星もすでに見つかっており、そこに海があり、生命がいるのかを調べることが次なる目標となっている。
僕は2030年代の初めまでには、これらのどこかで地球外生命が発見されるであろうと思っている。地球外生命の発見は、おそらくアポロ計画による有人月面着陸を超えるインパクトを、人類にもたらすであろう。僕たちが、広い宇宙で孤独な存在、そして何か特別な存在ではないということを証明することになるからだ。中高生が、そんな新しい学問を学びたいと思うのはよく理解できる。
実際、小学校から中学校、高校、大学へと進学するたびに、新しい学問が登場することを、皆さんも経験されたであろう。最初は単に理科だったものが、理科第一分野と第二分野に、高校では物理、化学、生物、地学と4つに分かれる。大学ではさらに細かく分かれていく。例えば、物理は、素粒子物理、物性物理、宇宙物理など、化学は有機化学、無機化学、材料化学といったように。僕の専門である地球科学も、気象学、地質学、地震学、惑星科学などへと分かれていく。
大学の学科に属する研究者も、基本的には細かく分かれた先にある、ひとつの分野を研究している。そして、驚かれるかもしれないが、同じ学科に属する研究者でも、細分化された先の学問については、専門以外ほとんど知らないことが多い。例えば、同じ地球科学科にいる研究者であっても、僕のような惑星科学の専門家が、地震学の最新研究を理解できるかと言われれば、実を言えばチンプンカンプンなのである。
さて、アストロバイオロジーを学ぶには、どの学科に行くべきか。ある学科の細分化された学問の先に行けば、どこかでアストロバイオロジーにたどり着くのであろうか。答えは否である。大学はもとより、大学院まで進んだとしても、細かく分かれた道の先にアストロバイオロジーなる学問は存在しないのである。では、アストロバイオロジーとはいったい何なのであろうか?
火星からの使者
アストロバイオロジーという言葉は、20世紀末に、NASAが使い始めたものである。これが誕生したきっかけは、火星から飛来した火星隕石(ALH84001)に微生物の痕跡と思われる物質を“発見”したと、ある研究者が発表したことにある。研究者の名はデイビッド・マッケイ、1996年のことである。彼は、火星の表面に存在していた岩石を手に入れ、電子顕微鏡と呼ばれるナノメートルサイズの物質まで調べることのできる特殊な顕微鏡で、それを緻密に分析したのである。
なぜ彼は火星の岩石を手に入れることができたのか。いきさつはこうである。
この火星隕石を含む岩石は、約36億年前の火星でマグマが冷え固まり誕生した。その後、約1500万年前に起きた火星への小天体の衝突によってこの岩石は宇宙空間に飛び出した。放出された岩石は長い間宇宙を漂っていたが、約1万年前、偶然欠片の一つが地球の南極に落下し、1984年に南極調査チームがこれを見つけ、最終的にマッケイ博士の手に届いたというわけである。壮大な時空間スケールの旅である。
この隕石は宇宙空間に飛び出すまでの間、火星上で様々な事象を経験したに違いない。36億年前の火星は今よりも温暖であり、水も一時的に存在していた。この隕石にも、火星上の岩石だったころに、火星の水や大気がその内部にまでしみ込んでいたのである。マッケイ博士は、この隕石の水がしみ込んだあたりに、微生物のように見える有機物を見つけた。その有機物は確かに鎖状に連なって、岩石の上を這いつくばっているようにも見えた。



この“発見”はすぐさまセンセーションを巻き起こした。これが果たして火星生命の痕跡なのか、様々な専門家たちが白熱した議論をくり返した。しかし、結局のところ、これが生命の痕跡であるのか、結論は出なかった。
結論は出なかったものの、マッケイ博士の発見には二つの大きな意義があった。
一つは、地球外生命という空想でしかなかったものを、科学の対象にできるということを実際に示した点である。火星や他の天体から、もっと保存状態のよいサンプルを持ち帰れば、今度こそ生命を発見できるのではないかと、誰しもが考えたのである。
その後、21世紀における太陽系探査の大目標として地球外生命の発見が掲げられ、これが大きな潮流となり現在に続いている。
そして、もう一つの意義こそが、アストロバイオロジーの誕生につながるものである。
というのも、火星隕石の議論の過程で、専門家たちは重要な事実に気が付いたのである。隕石中の物質が生命かどうか判断するには、極めて広い専門的知見を一つに束ねる必要があるということを。
火星生命の発見に必要なこと
火星生命の発見に必要な知見とは何であろうか。微生物学の知見はもちろんのこと、隕石がどんな温度を経験したのかという惑星科学の知見、火星の環境がどのようなものだったのかという地質学の知見、有機物は元々どんな物質だったのかという有機化学の知見など、いずれも火星生命の発見に欠くことができない。各専門家たちが互いの研究成果を理解し、知見を統合して、誰も見たことのない火星生命の姿を仮定し、そのうえで検証しなければならない。
しかし、これまで専門家たちは、それぞれ細かく分かれた学問の領域のみで生きていたのである。細分化された学問の間には目には見えない壁があり、専門家でさえ、いや専門家であるほど、壁を越えて他の分野に侵入するのは難しかった。なぜなら、素人同然の他の研究者に領空侵犯されることは不快であり、「嫌なことは相手にもしないでおこう」と考えるからである。微生物学者と惑星科学者の間にある壁の高さとなると、地震学と惑星科学の壁どころではない。微生物学は生物、惑星科学は地学の先にある学問分野であり、高校の時点でこれらは分かれている。地学のことを最後に勉強したのは中学生の頃という生物学者はたくさんいる。逆も同じである。
地球外生命に対峙する上で、必要なものは専門的知見をさらに深めることではなかったのである。むしろ、細分化されきってしまった知見を統合することが課題であり、難しさであった。17世紀のデカルトの時代以降、人類は自然をよりよく理解しようとして、対象や原理に基づき自然を細かく分けていった。その結果、多くの学問が生まれ、各分野の理解は深化したが、気が付かないうちに分断されていたのは、実は僕らの思考そのものであった。
微生物学者は、微生物とそれが這いつくばっている岩石とを切り離し、微生物のみを調べる。地質学者は、逆に岩石だけを切り出して、微生物を極力見ないようにする。しかし現実的には、それらはひとつなぎの自然現象であり、両者は相互に関連するのである。
地球外生命といった根源的な問いに対峙するには、物理学から化学、生物学から地球科学までを横方向にもう一度つなぎ合わせて、自然現象の全体像をとらえる大きな”視座”(物事を見る姿勢や立場)が求められるのである。アストロバイオロジーとは、まさに全体像をとらえようとする視座のことであり、17世紀以降の細分化した学問分野とは一線を画する。つまり、大げさに言えば、アストロバイオロジーとは視座であって学問分野ではない、というのが僕のたどり着いた答えである。
世界に広がる新しい流れ
1996年に発表された火星隕石の研究をきっかけに、専門家たちは手を取り合って連携していった。アメリカでは、NASAアストロバイオロジー研究所(NASA Astrobiology Institute、略してNAI)というバーチャル研究機関が1998年に発足し、現在までアメリカの28の大学や研究所がこれに加盟している。所属機関の顔ぶれは数年ごとに変化しているが、700名を超える研究者がこれに加わっている。各研究者の専門分野としても、物理学、天文学から、化学、生物学、地球科学、さらには情報科学や複雑系科学まで含んでおり幅広い。
NAIは海外にも連携パートナーをもっており、僕の所属する東京工業大学の地球生命研究所(ELSI)は、日本の大学では唯一のNAIの連携パートナーである(大学以外には、自然科学研究機構と日本アストロバイオロジー・ネットワークが日本の連携パートナーである)。研究機関だけではない。アストロバイオロジー科学会議(Astrobiology Science Conference)という関連研究者が一堂に会する会議も隔年で開かれている。次回は2021年にアトランタで開かれる予定であり、僕もオーガナイザーの一員となっている。
このような研究機関が発足し、会議が開かれれば、すぐさま皆がアストロバイオロジーの視座を獲得できるかといえば、もちろんそうではない。各人が他分野を領空侵犯し撃墜されようとも、くり返し一歩踏み出し、理解しようとする努力をつづけなければならないし、このような取り組みが真に実を結ぶのは僕の世代ではなく、その次の世代、つまり今、中高生の彼ら彼女らの世代かもしれない。
アストロバイオロジーのような、専門的知見を横に束ねて全体像を見渡すといった新しい学問の流れは、従来の学問の方向性である縦方向への深化とは本質的に異なる。そして現在、この新しい流れの必要性が多方面で増している。
環境問題、豪雨災害、そして新型コロナウイルスといった複合的な課題の解決には、アストロバイオロジー同様、広い専門的知見をひとつに束ねて、全体を見渡す視座が必要となる。全体を見渡す視座なしではこれら課題に対する大方針は決まらず、対処療法をくり返すことになってしまいかねない。
新型コロナウイルスという課題を例にしても、ウイルス学、医学、公共衛生学、地域文化学、経済学、そして政治までをも、その検討の範疇に含む。これらの専門家たちがメディアに登場して対策を論じるわけであるが、彼らがこうすればよいという正解を共有しているわけではないことに、皆さんも気づき始めているのではないか。僕は専門家の各種委員会に出たことがあるわけではなく、勝手な立場から想像するだけであるが、火星隕石の議論がそうであったように、現状、様々な専門家たちはお互いが主張することを理解するだけでも手一杯なのではないのだろうか。20年前以上にアストロバイオロジーが誕生したように、対象となるもの全体を見渡す視座をもち、大方針を決める人々をいかに生み出せるか。今、その仕組み作りが求められるのではあるまいか。
さて今回、三菱電機 DSPACEからコラム連載のお話しをいただいた。テーマは「アストロバイオロジー」としたい。アストロバイオロジーとは何であるか、今回のコラムで、皆様に漠然とでもお分かりいただけたのであれば、大変な幸せである。
“生命はどうやって誕生したのか、この宇宙に我々以外の生命はいるのか、どうやったら彼らに出会えるのか”
今後、これらの問いに迫る多彩な研究者たちの挑戦の数々をお伝えできればと思う。それらを束ねてみたときに、アストロバイオロジーというものの輪郭が、今より少しはっきりと見えるかもしれない。
我々の宇宙はビッグバンにより始まった。ビッグバン後に存在した素粒子たちから、陽子や中性子が生まれ、やがて水素原子が生まれた。そして約138億年後、無数にある銀河団のうちの、天の川銀河の片隅の太陽系の、その小さな青い星に僕がいる。
どうして僕にたどり着いたのであろうか。アストロバイオロジーはそれに答える物語りである。
- ※
本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。