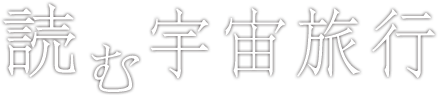系外惑星が大量に発見される時代の「系外生命」の探し方
5月中旬、「NASAのケプラー宇宙望遠鏡が系外惑星を新たに1284個発見!」というニュースが駆け巡った。そのうち9個は「ハビタブルゾーン(生命生存可能領域)」(惑星表面の水が液体で存在できるような主星からの距離。後に詳述)にあるという。このニュースに「生命発見の日は近い」とか「移住できる?」なんて記事まで出て大反響。確かにケプラー望遠鏡は系外惑星を大量に発見し、宇宙に惑星はあまねく存在することを観測により示したことは間違いない。そうなると次の期待は「第二の地球」に「宇宙の隣人」を探すこと。では具体的にどうやって「系外生命」(太陽系以外の生命)を探すのか。決して簡単ではないものの、その試みは既に日本で始まっている!その詳細を聞こうと、世界初の「アストロバイオロジーセンター」を国立天文台三鷹キャンパスに訪ねた。
直接撮像で突出した日本の系外惑星探査。次は「系外生命」存在確認へ
アストロバイオロジーセンターは自然科学研究機構の機関で、2015年4月に設立された。天文学だけでなく生物学や生命化学、地球科学など他分野と融合し、系外惑星における系外生命の存在確認を目指すことを中心に据えた組織は、世界初だという(NASAにはNASA Astrobiology Instituteがあるが、関連機関を結び付けたバーチャル研究所)。センター長は系外惑星探査の世界的第一人者である、国立天文台の田村元秀教授だ。系外生物の説明をする前に、日本の系外惑星探査の世界に誇るべき実績を紹介しておきたい。(残念ながら、一般にはあまり知られていないので・・)
それは、日本の系外惑星の「直接撮像」の実績だ。直接撮像とは明るい中心星をマスクで覆い隠して、暗い惑星の姿を浮かび上がらせ、惑星からの光を検出する観測手法のこと。これまで系外惑星は3000個以上発見されているが、そのほとんどは「間接的」発見だ。惑星が恒星の前を通り過ぎるときの明るさの変化(トランジット法と呼ばれ、ケプラー探査機の観測方法でもある)、惑星が恒星の周りを公転することで恒星がふらつく速度の変化(ドップラー法)から系外惑星の存在を検出している。
しかし、間接的な観測でわかることは限られる。惑星の詳細を知るには直接その姿をとらえる必要がある。そこで田村元秀さん率いるチームは、すばる望遠鏡用の新装置「HiCIAO(ハイチャオ)」や解析ソフトウェアなどを新規開発。2009年から5年間、大規模系外惑星探査プロジェクト「SEEDS」で観測した結果、4個の「直接撮像」に成功した。 これまで直接撮像された系外惑星候補は約50個。恒星から遠く離れた惑星が多く、太陽系で惑星が存在する範囲(恒星からの距離約100天文単位内)で直接撮像された惑星候補は、わずか約10個にすぎない。数が少ないのは難しいからだ。明るく光り輝く恒星のすぐそばで自ら光を出さない惑星を探すのは、灯台の近くを飛ぶ蛍を見つけるようなもの。その約10個の直接撮像のうち4個がSEEDSプロジェクトによるもの。これは日本の系外惑星探査の技術力の高さを物語っていると言えるのだ!さらに現在、ハイチャオの後継装置が稼働し始め、より暗く、より小さな惑星を直接撮像で発見しようと探査が行われている。

SEEDSで直接撮像に成功したのは「第二の木星」。日本が次に目指すのは「第二の地球の直接観測」だ。計画は二段階で進められる。第一段階は2016年夏に始まる。新しい観測装置IRD(近赤外高分散分光器)をすばる望遠鏡に取り付け、太陽系近くのM型星(太陽より軽い星)の周りでハビタブルゾーンにある地球型惑星候補を調べる。候補を絞り込んだら、次世代の超大型望遠鏡(TMT)で直接撮像も可能になると期待されている。いよいよ「系外生命」探査に向けた観測がスタートする。
「発見の時代」は終わり→惑星の「特徴づけ」の時代へ
アストロバイオロジーセンターの話に戻ろう。今回お話を伺ったのは、アストロバイオロジーセンターの堀安範(やすのり)特任助教。5月のケプラー望遠鏡の発表については「もう少しセンセーショナルなニュースだと思っていました。太陽サイズの星の周りで地球サイズの惑星がハビタブルゾーンに見つかったとか。でもそうではなかった。研究者的に言うと『数が増えただけか』と(笑)」。
堀さんによると、「以前は系外惑星が発見されただけでニュースになりましたが、系外惑星の発見から20年以上経った今は『発見の時代は終わった』と言えます。見つかった惑星がどういう性質を持っているか。岩石、大気があるか。大気があるとすればどんな大気か。水があるのか。表層環境や大気組成に迫る時代なんです」。
つまり、今は惑星の「特徴づけ」が焦点になっているということ。特徴づけに重要なのが惑星の大気を観測することだ。大気を分光観測し、大気に含まれる原子や分子を調べる。
「大気の分光観測が現在、系外惑星探査の主流になっていますが、近くにあるほど観測しやすい。恒星の明るさにもよりますが、地球から約100光年以内が一つの目安です」(堀さん)。ケプラー探査機で発見された系外惑星は数百~数千光年と遠い場所にある天体が多く、詳細観測は難しい。そこで、この夏すばる望遠鏡に搭載する新装置IRDは、地球から約100光年以内、つまりご近所を探査しようという目標を掲げている。

系外生命を探す二つの方法
近場の惑星を探す必要があることはわかった。次に生命がいるかどうかどうやって見極めるのだろうか。堀さんは生命活動を探るために現実的に可能な、二つの手法を教えてくれた。
「一つは大気の組成を見ることです。『酸素(オゾン)』と『有機分子(メタンなど)』があれば、生物的な活動が行われている可能性があります」とのこと。堀さんによれば、通常、惑星では火山活動があると二酸化炭素が増えるが、酸素は地質学的な活動だけでは自然には増えないという。地球上では約20億年前にシアノバクテリアが出現し、酸素を作った。それなら酸素が見つかればOKでは?なぜ有機分子も?
「一時期は酸素が見つかればOKと言われていました。でも水があった場合、紫外線で水が壊れて酸素と水素になり、軽い水素が宇宙空間に逃げて酸素が残る場合もあります。一方、有機分子は光合成のような生物的な活動がないとできない。今は、酸素と有機分子の両方あることが『バイオマーカー』だと言われています」
バイオマーカーとは、生物活動を示す「目印」のような物質のこと。ただし、酸素を検出するにはすばる望遠鏡のような大口径望遠鏡で十分な光を集め、感度を上げて観測する必要があり難易度が高いそうだ。「もし地球型の系外惑星の大気で酸素を検出したら大発見になります」と堀さん。
そしてもう一つの方法は、惑星大気の反射光から海や陸、植物があるなど、惑星表面の様子を大まかにマッピングすること。「雪は反射率が高いし、海は低いなど、表面の状態によって反射率が違います。特に注目するのは植物です。赤外線あたりで急激に反射率があがり『レッド・エッジ』と呼ばれます。これが観測されれば地球に似た植物がいる可能性が高いということです」。レッド・エッジ!なんとクールな響きだろう。しかしレッド・エッジ検出は、光量がカギとなるため、TMTで狙うサイエンスになるとのこと。そのための装置開発も始まっているそうだ。

IRDへの期待—大気組成を観測できれば世界初!
では実際に、この夏、すばる望遠鏡にとりつけられる観測装置IRDで系外生命の観測は可能なのだろうか?「これまでスーパーアース(巨大地球型惑星)の大気観測は5例ありますが、それよりも小さな地球サイズやハビタブルゾーンにある惑星の大気観測例はありません。でもIRDではそれらの惑星での大気観測が可能になると思っています。」(堀さん)いきなり生命探査というわけではなく、まず惑星の大気観測に迫るというわけだ。
なぜ大気観測が重要か。大気を調べれば、生命が存在可能かどうかを知る一つの大きな手がかりになる。と同時に 堀さんは「ハビタブルゾーンの罠」について話してくれた。「よくニュースでハビタブルゾーンにある惑星が見つかったと言われますよね。でもあれは地球のような大気をもつ惑星の場合であって、大気の組成が違えば、話はまったく違ってしまうんです。極端に言えば、地球だって温室効果ガス(特に水蒸気)がなかったら、今の地表面の平均気温15度はマイナス18度になってしまう。だから地球の大気組成が少し違えば、地球が今の場所にあっても、ハビタブルな環境とは言えなくなる可能性だってある。逆に地球より遠い位置にあっても二酸化炭素が多かったりして温室効果が強く働けば生命存在可能ともいえる。つまり、『大気組成を見ないことには何も始まらない』のです」
IRD(近赤外高分散分光器)は、太陽より軽いM型星(赤色矮星)をターゲットとし、直接撮像は行わず、ドップラー法で地球型惑星候補を洗い出し、その大気を調べる。なぜM型星をターゲットにするかと言えば、太陽型の恒星に比べて10倍ぐらい数が多いから。M型星は太陽より暗いため、そのハビタブルゾーンは地球―太陽の距離の十分の一ぐらい。太陽系で言えば、金星より内側を回る惑星となる。公転周期、つまり1年は2週間ぐらい。ドップラー法では惑星の軌道を決めるため1年間観測する必要があるが、2週間で観測可能となれば、効率的な観測が可能となる。しかし、星に近く、1年が2週間の惑星とは、いったいどんな環境なのだろう?
「M型星の周りの惑星は、地球の周りの月のように、いつも同じ面を恒星に向けていると考えられます。そのため昼と夜が固定されます。恒星を向いている面はずっと昼、反対側はずっと夜です。生き物がいたとしても生きられないのではないかとも考えられましたが、大気があれば熱は循環しますし、クマムシの例ではありませんが、生命は思ったよりタフであることがわかってきました。初期の生命(古細菌)は熱水噴出孔や温泉といった高温の極限環境で生存していて、地球は過去に少なくとも3回全球凍結したにも関わらず、生命は生き延びています。そこで、太陽系でも木星の衛星エウロパや土星の衛星エンセラダスの氷の下の海に生命存在の可能性が示唆されています。多様な環境でどんな生物がありえるのか、生物学と天文学・惑星科学の両方の知識が重要になると思います」
アストロバイオロジーセンターは現在、天文学者を中心とした約10人の小さな組織だが、今後は生物学者の研究者も増えていく予定だという。「天文学者は惑星の環境がわかります。その情報をもとに、生物学者はどんな材料からどんな生物がどう生まれるのか、その過程がわかるでしょう。つまり材料がわかれば、クッキングの方法がわかる。天文学と生物学はそれぞれ独自に進んできましたが、融合が必要な段階に来ていると思います」と堀さんは言う。
楽しみな時代になってきた。まずはこの夏、すばる望遠鏡に搭載される期待の装置IRDとその観測に注目だ。そして天文学だけでなく様々な学問と連携して生命の探査に迫ろうとする、アストロバイオロジーセンターの今後もウォッチしていきたい。