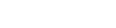Vol.3
火星探査の新時代の幕開け — 「忍耐」という名の探査車
2020年7月30日、アメリカ合衆国フロリダ州のケープ・カネベラル空軍基地から、1基のアトラスVロケットが打ち上げられた。ロケットに搭載されていたのはマーズ2020、別名「パーサヴィアランス」という愛称をもつ新しい火星探査車である。
しかし、この海の向こうのロケット打ち上げのニュースが、日本を始め各国で大きく報じられることはなく、一般から注目を集めることもなかった。
折りしも日本では、新型コロナウイルス感染症の拡大第二波の只中にあり、連日メディアは、社会最大の関心事である感染の動向や経済への影響について報じていた。これをお読みの皆さんも、そんなものが打ち上げられたのかと、今初めて知った方も多いかもしれない。
注目を集めなかったもう一つの理由には、火星探査がもはや珍しい出来事では無くなったこともあげられよう。
過去5年間だけでも、5機の火星探査機が打ち上げられている。2020年には、上記のパーサヴィアランスに加え、アラブ首長国連邦(UAE)の周回機、中国の周回機・探査車も打ち上げられた。日本では、UAEの周回機が多少話題となった。種子島宇宙センターで、日本の誇るHII-Aロケットにより打ち上げられたからだ。
しかし僕は、数あるこれまでの火星探査のなかでも、パーサヴィアランスは他と一線を画すものだと考えている。というのも、大袈裟にいえば、これにより火星探査の新時代が幕を開けると予想されるからだ。
ところで、パーサヴィアランス(perseverance)とは、「忍耐」を意味する言葉である。これまで過去の火星探査車には、「好奇心」を意味するキュリオシティや、「好機」を意味するオポチュニティといった愛称が付けられてきた。数多のリスクが内在する太陽系探査において、「忍耐」は決して縁起がよい言葉とは言えない。なぜ「忍耐」という名が探査車につけられたのだろう。
今回は、パーサヴィアランスが拓く火星の新時代の話をしよう。これを読み終えたときには、「忍耐」こそこの探査車の名にふさわしいと、皆さんにも思っていただけるに違いない。

火星は水の惑星だった
火星は、かつて水の惑星だったと言われる。だが、なぜそう言えるのだろうか。
これまで人類が送り込んだ周回機は、火星の周りを回りながら写真を撮り、地表にどんな地形があるのかを調べてきた。2006年に到着した周回機マーズ・リコネッサンス・オービターは、地球の衛星画像と同程度以上の詳細さで、火星表面の画像を取得している。火星上に1メートル程度の物体があれば形がわかるレベル — すなわち仮に、そこに人間が横たわっていてもそれと認識できるレベルで地表面が調べられているのだ。
このような高解像度で火星を眺めると、色々なものが見えてくる。大小さまざまな河川の跡、それらが注ぎ込んでいた湖の跡。さらには、川で削られた谷やクレーターの壁に見える地層に、どのような物質があるかも見えてくる。見えてきた物質とは、粘土や塩など、地球上では液体の水があることでできる物質である。粘土は岩石に水が長時間触れ合うことででき、また塩は岩石から水に溶けだしたミネラルである。河川や湖の跡、粘土といった、水が地表に存在した痕跡が観測されるのは、地球を除けば、太陽系では火星だけである。
周回機だけでなく、探査車たちも火星に降り立っている。2004年にはオポチュニティとスピリットという探査車が、2012年には探査車キュリオシティが、それぞれ火星に着陸している。探査車はかつての湖の底の粘土の上を走り回り、周回機だけではわからない地下浅部に存在する物質や、粘土や塩の成分からかつて存在していた水のpH(ピーエイチ)や溶存成分を調べる。さらに、生命を形作る有機物が地層中に含まれるのかも調べている。
顕微鏡で地層を観察し、サンプルを採取するその姿は、さしずめ火星に降り立ったロボット地質学者といったところだろう。
45億年の火星大進化
このような周回機と探査車のコンビネーションによって、火星の環境の歴史が復元されている。その大まかな描像はこうである。
約40億年前の火星では、海のようなまとまった量の水は地上にはなく、広範囲に地下水が存在していたと考えられている。水のpHは中性から弱アルカリ性で、地球の地下水によく似た成分をもっていた。当時の火星は地下水の惑星だった。
その後、約38億年前には、地下だけでなく、地表面にも液体の水が豊富に存在するようになった。この時期に多くの河川が作られ、泥が湖や海に運搬されて粘土などを含む地層が作られていった。火星が最も地球に似ていた時代である。
しかし、約35億年前ごろになると、火星全体が急速に乾燥・寒冷化する。水が存在する地域はまばらになり、その水のpHは僕らの骨も溶かすほどの強い酸性の水となり、“酸の湖”が点在する惑星となっていく。そして、それ以降ではもはや水の痕跡はなくなり、現在のような砂漠が広がる惑星になっていった。

火星の環境は、地球に住む僕らの想像をはるかに上回るほど劇的に進化していたのである。 同時に、このような火星の進化史がわかると、次のような疑問もわいてくる。
— 水が豊富にあった約38億年前に火星生命は存在したのだろうか。
— なぜ火星では急激な環境変化が起きてしまったのか。将来の地球でも起きるのだろうか。
— 生命は今でも火星のどこかに生き延びているのだろうか。だとすれば、どこに。
パーサヴィアランスの戦略
2020年7月に打ち上げられた探査車パーサヴィアランスは、このような疑問に答えようとするものである。火星生命を探す生命探査だといってよい。
ありていに言えば、これまでの火星探査車はロボット地質学者であり、行われたのは地質調査であった。ところが、これまでと同じ地質調査では、生命まで含む疑問に答えることはできない。ごく微小であろう火星生命の存否を明らかにすることのできる分析装置は通常、大掛かりなもので探査車に搭載できるサイズではない。
では、どうすればよいか — 答えは「火星のサンプルを地球に持ち帰る」ことである。
“何だ、そんなことか。探査機「はやぶさ」がやったことではないか”と、皆さんは思われるかもしれない。
しかし、太陽系探査において、ほとんどの場合、探査機は地球に帰還したり、サンプルを持ち帰ったりはしない。探査機はその探査天体に置き捨てられるか、あるいは故意に天体に衝突させて破壊することで、その一生を終える。
「はやぶさ」は、地球近傍の小惑星を訪れたため、限られた動力でも地球に帰還することが可能だった例外の探査である。
重力の大きい火星からサンプルを持ち帰るのは、小惑星からそれを持ち帰るのとはわけが違う。サンプルを持ち帰るためには、まず火星からサンプルを積んだロケットを打ち上げ、それを火星軌道で別の宇宙船がキャッチし、それが地球まで届けるという途方もない技術の積み上げと挑戦が必要となる。
火星サンプルリターン計画
それをやろうというのが、この探査車パーサヴィアランスである。
より正確には、パーサヴィアランスはその先駆けである。火星上でサンプルを採取し、事前分析を行ってサンプルを峻別し、小さな帰還用カプセルにサンプルを保管するのが主な役割だ。


その後、2027年にパーサヴィアランスの着陸地点の近くに無人のロケット発射台が建てられる。そのロケットは採取した帰還用サンプルを載せる。同じ2027年には、火星軌道上でロケットから打ち上げられたサンプルをキャッチする無人宇宙船が待機し、2031年にサンプルを地球に持ち帰るのだ。
この一連の計画を「火星サンプルリターン計画」という。NASAと欧州宇宙機構(ESA)が、威信をかけてこれを進めている。パーサヴィアランスの打ち上げは、この計画のまさに幕開けといえるだろう。火星からサンプルを自在に持ち帰るというこの探査方式が確立すれば、火星の探査は新時代を迎えることになる。
パーサヴィアランスの着陸予定地点は、約38億年前に広大な湖をたたえていたジェゼロ・クレーターという盆地である。この盆地の湖に注ぎ込んでいた河川がつくった三角州に着陸しようとしている。かつて、この湖に生息していた火星生命の痕跡を僕たちが発見できるとすれば、火星からサンプルが帰還する2031年ごろとなろう。これは同時に、人類による初めての地球外生命の発見となるはずだ。


火星生命だけではない。火星サンプルリターンは、当然のごとく宇宙飛行士による有人火星探査へと発展していく。サンプルを安全に持ち帰るということは、宇宙飛行士を安全に地球から火星、また火星から地球へと輸送する技術の獲得にもつながるからだ。
実は、探査車パーサヴィアランスは、2030年代に計画されている有人火星探査のための重要な布石ともいえる装置も搭載している。が、この装置や有人探査の話は、次回に取っておこう。
パーサヴィアランスは、2021年2月に火星ジェゼロ・クレーターに着陸し、探査を始めるだろう。火星の冬はマイナス60℃以下の極寒であり、猛烈な砂嵐が舞う日も多い。そんな過酷な環境にじっと耐え、自分以外に動くものがない中を1000日以上、孤独にひたすら待つことになる。
いったい何を? — 2027年に来るであろう仲間のロボットや、2030年代に来るであろう宇宙飛行士のことを。
この探査車を待ち受ける運命を考えると、やはり「忍耐」という名こそふさわしいのだろうと、僕は思う。
- ※
本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。