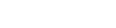Vol.13
妖怪とアストロバイオロジー I “天狗”
僕が三菱電機DSPACEで、この連載コラムをもってちょうど1年が経つ。
「アストロバイオロジー」を通じて、宇宙、生命、そして僕ら自身を俯瞰することがこのコラムの主題であるが、こういう漠とした主題はコラムにはなりにくく、なりにくいままに連載が進んでいる。結果的に、多彩な研究者たちのスナップショットを集め、それを点描のように張り合わせている。
もっとも、点描を張り合わせるのは読者の皆さんであり、書き手として情けない話であるが、皆さんが点描から多彩な全体像を描いてくれるのを願うしかない。
さて、1年が経った今、ここらで少し休憩して、雑談を挟みたい。
今回は、妖怪というものをアストロバイオロジーの観点から考えてみたいのである。
個人的な趣味で恐縮だが、僕は民俗学や文化人類学に関連した書籍や話が好きであり、民俗学の一領域を占める妖怪の研究と、地球科学やアストロバイオロジーの接点がないものか、誰に発表することもなく密かに探している。
とはいっても、妖怪=宇宙人、といった荒唐無稽な考えを述べるつもりはない。
妖怪とは、もともと古代中世において、人智を超えた出来事や物に対して名付けられた名称である。理解不能な出来事を物の怪(もののけ)がおこしたと理解することで人々は安心し、また子供の教育にもなった。
例えば、ぬりかべとは九州北部の妖怪であり、夜に砂浜辺などに出歩くと身動きがとれなくなる出来事をいう。“夜に浜に行くと、ぬりかべが出る”と子供に言うことで、危険から子供を遠ざけさせる効果もあったのだろう。
しかしながら、当時の人智を超えた出来事も、現在の科学から見れば自然現象の1つとして理解されることも多い。
今回は、日本人なら知らない人のいない“天狗”の起源が、科学でどのように理解できるのか、僕の実験にお付き合いいただきたい。
天狗の起源
天狗、と聞いて皆さんは何を思い浮かべるだろうか。
深山に棲み、鼻の高い赤面で下駄を履き、背の翼で自由に空を飛ぶ — このような姿が多くの皆さんの思う天狗であろうか。
実は天狗を始め、妖怪のイメージは時代と共に進化してきた。
現代の僕らが抱く天狗のイメージは、平安時代以降に出来上がったものであり、山で修行する山伏がその原型となったとも言われる。
最も古い天狗に関する記述は古代中国にある。紀元前100年ごろの前漢、武帝の時代に司馬遷が書いた歴史書「史記」に天狗の記述がある。要約するとこうである。
“天狗(てんごう)とは、夜、突然轟音と共に空が光る出来事である。それと共に地面に丸い大穴が開き、穴の中心に真黒く石化した犬が横たわっている。石の上部は細く伸び、黄色みを帯びており、尾のごとくある。これは天を走る狗(いぬ)が地上に落ちたものであり、これがあると近隣で将軍が死ぬなど不吉なことがおきる”

お気づきだろうか。これはまさに隕石落下の描写なのである。
飛鳥時代の「日本書紀」には、日本で初めて天狗について書かれた次の記述がある。
“京都の空に、突然天を割くような轟音と光が現れた。人々は何事かと話し合ったが、判然としない。そのとき中国から来た高僧が、あれは天狗(あまついぬ)、つまり天を走る犬であり、鳴き声が雷に似ているのだ、と説明したという“
その後、平安時代の「宇津保物語」や「大鏡」では、天狗の形態が進化する。深い山々から突然聞こえる不思議な音は天狗という悪霊が発したものであり、その天狗は山で人を惑わせる、とある。遣唐使の廃止以降の日本文化と同様に、中国とは別に、天狗も日本で独自の進化を始めていくこととなる。
隕石の落下
さて、惑星科学的な観点から述べれば、隕石の落下は太陽系において、最もありふれた自然現象といえる。
火星軌道と木星軌道の間には、小惑星帯と呼ばれる無数の小天体の群れがある。小惑星帯では、小天体同士が時折衝突し、大小無数の破片が宇宙空間に放り出される。
その放り出された破片のうち、偶然地球に落下し、地上までたどり着いたものを隕石と呼ぶ。

ごく小さな破片は地上までたどり着くことはできず、大気との摩擦で燃え尽きて、空に光の筋のみを残す。空に残った光の筋を火球と呼ぶ。
火球は、近年ではしばしば目撃されている。街を映すカメラや車のドライブレコーダが増え、その結果、火球が撮影される機会が増えている。隕石落下については、約8年前のロシア・チェリャビンスク隕石をご記憶の方も多いだろう。このときは1000人以上の負傷者がでた。6550万年前の白亜紀末の大量絶滅、恐竜を滅ぼしたのは直径10キロメートルほどの大きな隕石の落下であった。
実は僕も高校生のとき、隕石の落下を体験した。1996年1月に茨城県に落ちた「つくば隕石」がそれであり、僕はそのとき埼玉県内にいて、あまりの轟音に飛び上がって驚いたことを鮮明に記憶している。つくば隕石の火球は、東北から北陸までの範囲で人々に目撃された。
隕石が地球に落下する頻度は、隕石のサイズが大きくなるにしたがい低くなる。つくば隕石程度の大きさの天体は、年間10個ほど地球に落下している。しかし、ほとんどが海上などに落下しているので、僕らが気付くことはない。司馬遷「史記」に登場する隕石を、仮に直径1メートル、10トン程度とするならば、そのような隕石は1年に一度の確率で地球のどこかに落下している。
人生をおよそ100年とすれば、人生に一度程度、火球や隕石落下に実際に遭遇することは十分ありうることだといえよう。

荒ぶる小天体
この人生に一度という頻度が、天狗という妖怪の誕生には重要だったのではあるまいか。
仮に、隕石落下の頻度が高く、しばしば起きる出来事であれば特異性は薄れるだろう。逆にその頻度が低く、数世代に一度起きるかどうかの出来事であれば、それは人々に伝承されにくい。
地球への隕石落下の頻度は、小惑星帯にある小天体の個数に比例する。もし、小惑星帯に今よりずっと多くの天体が存在していれば、小天体同士の衝突も頻繁に起き、その分、地球への隕石落下の頻度も上がるというわけである。
では、そもそも小惑星帯の小天体の数はどのように決まったのであろうか。
実は、この問いに対する答えは出されていない。太陽系のでき方を研究する太陽系形成論によると、現在の惑星たちができる前の原始の太陽系には、無数の小天体が存在していたとされる。その後、小天体同士が合体し、惑星を作っていくわけだが、惑星ができる過程でどのくらいの数の小天体が合体を免れて生き残るかは、ほとんど偶然が決めているらしい。小天体が多く残るような惑星系も、また逆に小天体が残らず、小惑星帯も存在しないような惑星系も理論上ありうるという。
恐竜を滅ぼした直径10キロメートル程度の巨大隕石の落下は、地球ではおよそ1億年に一度の頻度で起きる。小天体がたくさんある太陽系外の惑星系では、この頻度がずっと高く、例えば数百万年に一度ということもあるだろう。生物学的に人類がチンパンジーと分かれたのが約600万年前といわれており、仮に太陽系が小天体にあふれる惑星系だったならば、人類は破滅的な巨大隕石の衝突を人類史のどこかできっと経験していた計算になる。
逆に、太陽系が小惑星帯のない惑星系であれば、巨大隕石衝突の頻度はずっと低く、哺乳類の時代は未だもって訪れていなかったであろう。
太陽系には絶妙な数の小天体が残ったことにより、地球ではある頻度で生態系の建て替え ― スクラップ&ビルドが起き、その結果、今では哺乳類が繁栄し、人の一生に一度程度の頻度で隕石落下を体験することで、天狗という妖怪が誕生しえたともいえる。

科学は妖怪を滅ぼすか?
科学の進展により、人智を超えた出来事であったものが、自然現象として理解されている。その意味において、現在、妖怪の出る幕はなくなった。何か不思議な出来事が発生しても、それを引き起こしたとして新しい妖怪の存在が広く提唱される余地は現代社会にはない。
はたして科学は、妖怪を滅ぼしているのだろうか?
僕の考えは、否である。かつて人々が妖怪を想定したのは、不思議な出来事を論理的に理解したいためであった。この人類の好奇心や想像力の営みは、今でも何ら変わらない。
かつて人々が深山に棲む天狗を想像したように、僕らは小惑星帯の小天体たちを想像する。天狗が咆哮する姿を想像したように、恐竜を滅ぼした巨大隕石を想像する。
天狗は僕らにとって小惑星帯の小天体そのものであり、その本質は何ら変わっていないのではなかろうか。
むしろ、知が深まる分だけ、想像も深まっている。僕らは小天体が数多ある惑星系や、それらが極端に少ない惑星系を想像し、そこで生きる生命たちの運命を考え、地球や人類の置かれた幸運や不思議さを思う。
明治大正の物理学者であり随筆家、寺田寅彦いわく、
“科学とはやはり不思議を殺すものではなく、不思議を生み出すものである”
とは、まさに言い得て妙であろうと思う。
- ※
本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。