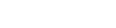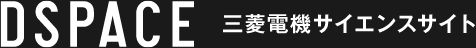Vol.53
スポーツと、宇宙と、生命の進化
去る2025年2月19日、世界的にも面白い協定の調印式があった。日本のスポーツ庁とJAXAとの間の連携協定であり、僕もその調印式に参加させていただいた。
スポーツと宇宙に一体どのような関係があるのだろうかと、皆さんは意外に思われるかもしれない。ところが、それが大いにあるのである。
低重力の宇宙空間で、筋力や骨密度が低下することはよく知られている。この状態で宇宙飛行士が地上に帰還すると、重力に打ち勝てず自力で生活することが難しい。それを防ぐため、国際宇宙ステーションでの宇宙飛行士のスケジュールには、毎日2、3時間のトレーニングが組み込まれている。つまり、宇宙ではスポーツが義務付けられているのである。
それだけではない。宇宙においてスポーツをすることは、宇宙空間への順応、チーム作り、ストレス軽減など、宇宙における人間らしい生活—ウェルビーイングの実現に無二の効果がある。火星に人類が行く場合、片道数か月の移動期間の無重力生活を経て、その後、2年間の火星生活を送らねばならない。生活をサポートしてくれる地上スタッフは火星にはおらず、大きな火星重力に晒されながら、自分たちで助け合い生き延びねばならない。スポーツは火星までの旅での筋力減少を防ぐだけでなく、互助共助を可能にするチームを作るためにも必要である。
これから宇宙は、間違いなくずっと身近になる。アルテミス計画のもと、多くの宇宙飛行士が月、さらに火星を訪れる。宇宙飛行士だけではない。民間による宇宙開発や宇宙旅行などの宇宙事業も本格化し、宇宙機関の正式な宇宙飛行士でない人々も、フライト前後にトレーニングを受けることになるだろう。
そう考えると、今、スポーツと宇宙が連携することは、これほど時宜を得たものはないと思えてくる。今回は、このユニークなスポーツと宇宙の連携内容や、これに対する僕の期待を述べてみたい。

スポーツと宇宙の連携協定
このスポーツと宇宙の連携協定であるが、これを強力に主導したのは、室伏広治スポーツ庁長官である。もはや説明不要であろうが、室伏長官は2004年アテネ五輪のハンマー投で金メダルに輝き、2012年ロンドン五輪においても銅メダルを獲得した。陸上・投てき種目でのアジア人初となる金メダリストであり、日本における最も著名なアスリートの1人である。
同時に僕は、彼がスポーツ科学分野の一流の科学者でもあることも、皆さんに知っていただきたい。多忙な長官職を務める傍ら、年間数本の学術論文を筆頭著者で執筆し、いずれも著名な国際誌に発表している。科学者としてみても、彼ほどのアクティビティを持った人を探すのは難しいのではなかろうか。
室伏長官の構想である今回の協定の内容を簡単にまとめると、以下の6点になる。
- パラアスリートを含めたトップアスリートと宇宙飛行士の一体的な強化
- “一器多用”の観点を踏まえた、宇宙での人間の能力拡張
- 宇宙飛行士・アスリート間の健康管理とコンディショニングの技術連携
- 宇宙での平和的スポーツ交流、宇宙空間での新スポーツ開拓
- 宇宙スポーツを行う上での国際ルール作り
- 人類の宇宙進出の知見・技術による地上の人々のライフパフォーマンスの向上
いずれも画期的な内容といえる。トップアスリートのための施設には、低酸素室や人の動作解析・計測装置がある。これら先端施設を宇宙飛行士と共用できれば、いかにも効率的であろう。人類が持つ最高峰のトレーニング技術や健康管理法を共有し、仮に宇宙でのトレーニング時間を短縮できれば、その分、実験や船外活動を増やすことができ、余暇の時間も生まれうる。
また、月面や火星で行う新スポーツは、エンターテインメントとしても魅力的である。宇宙大国による競争の色合いが濃厚な宇宙開発において、オリンピック・パラリンピック精神のもと、宇宙を平和に利用することができればそれはスポーツを超えた意義があるだろう。
しかしこれら項目のなかでも、僕が特に心惹かれたのは「“一器多用”を踏まえた人類の能力拡張」という部分である。

一器多用
一器多用とは、文字通り、1つの道具に多くの用途を見出すことであり、工業デザイナーの秋岡芳夫氏の概念だといわれる。1つの道具に1つの用途を限定する欧米の機械論的な考えではなく、たとえば箸のように、単純な道具を単純であるがゆえに柔軟に、複数の用途に使ってしまうというもので、いかにも冗長性を愛してきた日本的、あるいはアジア的な発想といえる。
調印式には、パリ・東京パラリンピックのパラ水泳金メダリストである木村敬一選手もいた。彼のスピーチは感動的であったが、そのなかで以下のようなことを言った。
“パラアスリートは体のどこかに障害を負っているが、それ以外の残存する機能の能力を存分に鍛え上げることで、パフォーマンスを高め、新たな感覚を開拓し、人類のポテンシャルを引き出す。これらの知見は、同様に感覚や機能が制限される宇宙における人間の感覚や機能の向上に、多少なりとも役立つのではないか”
木村選手は先天的に視覚に障害を持つが、指先の感覚で空間を認識し、進むべき前方を確認するという。触覚を使って空間認識をするという意味において、指が眼の役割も兼ねる“一器多用”だというのである。
これに宇宙飛行士の野口聡一氏も答える。国際宇宙ステーションの船外活動において音は聞こえないが、仲間がフックでステーションを叩く振動を指先で感じ、仲間の存在位置を認識するのだという。この場合、指先が耳の役割を兼ねている。
日本伝統の演劇である能においても、能面で視覚が制限されるなか、摺り足やひざの向きで正面を探る。以前、僕はこの話をNASAのロボット工学者に話したところ、ロボットにおいても同様に、各部位の動作方向で方角を探ることができるのだという。
我々は、機械論的に、すなわち用途の決まった部品の集合体として、自らの身体を理解したがる。しかし、そのような一器一用ではない機能や能力が、人間には明確に備わっている。人間の持つ一器多用性とは、きっと進化の過程で生まれた生命の持つ冗長性であろう。
生命の冗長性と進化
宇宙という異なる環境においては、人間が本来持つ冗長性を存分に活かし、柔軟に環境を認識し、適応しなくてはならないということを改めて思わされる。スポーツとは、そのような冗長性が生み出す機能や感覚を最大化する技術であり、その限界を突破していく挑戦だといっていい。人類の新たな可能性を拡げるという意味において、スポーツと宇宙には大きな共通点が存在している。両者がここに連携するというのは、至極、理に叶っている。
思えば、地球生命史とは、まさにそういった環境の変化に対し、生命が冗長性を活かして機能や感覚を創造していく歴史そのものであった。
例を1つ、2つあげたい。約2億年前のジュラ紀は恐竜の世界である。ジュラ紀の大気酸素濃度は低い。現在20%の酸素が、当時は13%ほどしかなかった。それでも恐竜たちが活発に運動し得たのは、気嚢(きのう)による呼吸システムを持っていたことによるといわれる。
気嚢とは肺の前後にある、新鮮な空気を溜めつつ効果的に肺に流す袋のようなものである。低酸素下の地球においてこの気嚢は最大化され、恐竜の骨の内部にまで及んだ。結果、骨がスカスカの空洞ができる。恐竜は低酸素下でも高い運動能力を保ち、繁栄する。
その後、白亜紀末から新生代に至り、酸素濃度は現在と同程度まで上昇する。すると、恐竜が持っていた気嚢システムは明らかにオーバースペックとなった。
恐竜の子孫である鳥類は、オーバースペックとなった気嚢システムの冗長性を利用して、全く新しい機能を創造した。飛翔である。
スカスカの骨は体重を軽くし、空を飛ぶことを可能にした。気嚢のおかげで、酸素の薄い上空数キロメートルでも鳥類は激しく羽ばたくという運動を可能にした。
遥か原始地球においても、別の例を見ることができる。海底熱水噴出孔に生息した原始的な微生物は、熱水に含まれる食料を効果的に得るため、その熱(赤外線という光)を感知する機能を持った。微生物はその後、海底の熱水環境を離れ、浅海という異なる環境に飛び出した。あるいは、現実的には、たまたま放り込まれてしまったのかもしれない。そのとき、元々持っていた光を受容する機能を用いて、太陽光からエネルギーを得る光合成という新機能ができたのではないかという仮説もある。

月や火星において、地球の1Gのための僕らの体は、明らかにオーバースペックである。しかし、オーバースペックであるがゆえに、僕らは自分の体を一器多用に使い、鳥のように、新しい機能を生み出すかもしれない。月で、火星で、人類はどのような機能や感覚を拡張していくのであろうか。
パラ宇宙飛行士

パラ水泳の木村敬一選手は、調印式で次のようにも言った。
“無重力の宇宙では、地上で障害者と呼ばれる人の障害が打ち消されるのではないか。下肢に障害がある人も、無重力では、水中でそうであるように、自力で移動できるだろう。無重力が障害を打ち消すのであれば、宇宙とは、誰も経験していない圧倒的なバリアフリー空間なのではないか。そこで新しい宇宙スポーツができれば、障害者も、そうでない人も、等しく楽しむことができるのではないかと、ワクワクしてしまう”
2008年の北京パラリンピック、陸上100メートル走で銅メダルを獲得したジョン・マクフォールは、2022年、欧州宇宙機関(ESA)が訓練する予備宇宙飛行士に選ばれた。この調停式の直前、2025年2月に彼は国際宇宙ステーションの医療認定を受け、整形外科医として長期宇宙ミッションに参加できる宇宙飛行士として認定された。初のパラ宇宙飛行士である。
木村選手はさらに続ける。
“健常者前提で出来上がるシステムに、障害者が後から参加することには多くの障壁がある。宇宙開発はすべての人が宇宙にアクセスできる成長段階にあると思う。この段階から、私たち障害者が関われることに大きな意味を感じている”
- ※
本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。