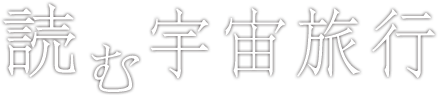「生き辛さを抱える人に光を」野口宇宙飛行士らが取り組む当事者研究

「なぜ我々はこんなに生きづらいのか。そんな思いを持った人々に何らかの明かりを当てられれば」。東京大学先端科学技術研究センター(以下、先端研)特任教授に着任した野口聡一宇宙飛行士は、2022年1月5日に行われた会見で研究の目的を語った。
野口さんの研究分野は「当事者研究」。約4年前から東大先端研准教授で身体障がい当事者である熊谷晉一郎氏と共に研究を進めてきた。
当事者研究ってなんだろう?熊谷准教授によれば「従来、一方的に研究される対象だった障がいをもった人たちが、自分たちの苦労や解決法について『当事者として』自ら研究するという新しい挑戦を表す分野」だという。だが、自らの経験を言葉で伝えようとする時、世間で広く使われている言語はマジョリティの経験を伝えるには便利な一方、マイノリティの経験を伝えるにはうまくあてはまる言葉が存在しない。「言葉や知識は人類の豊かな経験のレパートリーに追いついていない」熊谷准教授はそう指摘する。特に見えにくい障がい、精神や発達の障がいの分野において。「これまで誰も言葉にしてこなかったことを言葉にする。そこに挑戦するのが当事者研究」だと。
「当事者研究」の当事者とは、狭い意味での障がい者だけではない。宇宙飛行士やトップアスリートは、障がいはないかもしれないが言葉や知識が追い付かないレアな経験をもった人たち。彼らから学ぶべき点があるのではないか。「新しい当事者研究に踏み出そう」という目的のもとに、野口飛行士が特任教授として2021年12月に着任したのである。
宇宙飛行士の職場から障がい者の職場が学べること

豊富な宇宙経験をもつ野口飛行士に当事者研究で期待することは何か。記者会見で熊谷准教授は二つの点をあげた。一つは組織運営。「ISSは大きな失敗をすれば命が失われる、つまり失敗が許されない組織でありながら多様なバックグラウンドをもった乗組員が喧嘩せず協力し合っている『高信頼性組織』の代表例。高信頼性組織の知見が障がい者就労の現場に非常に参考になるのではという気運が、イギリスを中心に高まっている」という。
具体的には?熊谷准教授は高信頼性組織に必要な条件の一つである「ジャストカルチャー」という考え方を説いた。「重い障がいをもった人々の就労現場では、失敗に対して寛容であるけれども無責任ではない文化(ジャストカルチャー)が職場の条件として成り立つのではないか、とここ10年程言われている」。つまり誰かが失敗をしたときに、その人を責めて排除するのではなく、その失敗がどういうメカニズムで起きたのかみんなの問題として膝を突き合わせて考えるのがジャストカルチャーだと。
これは小児科医である熊谷准教授自身の当事者研究でもあるという。「私は高信頼性組織の一種である医療現場で働いてきた。失敗が許されないのに(自分は)障がいがあり手が不自由。それでも働ける職場と働けない職場があった。その違いはなんだろうとふり返った時に『高信頼性組織』の条件がすごくいい線をいっているのではないか。その極地がISS。そこから是非学んでみたい」。まだ誰もやっていない挑戦であり着想段階だそうだが、宇宙開発がこういう形で貢献できれば素晴らしい。

そして熊谷准教授が期待する2点目は「ライフコース」。宇宙飛行士やトップアスリートは人生のある一瞬だけに焦点があたりがちだ。しかし、そのあとも人生は続く。それは高齢者社会を生きる私たちも同じこと。現役引退後の長い人生でどういう暮らしを営んでいくのか、というヒントを得られるのではないか、と。
船外活動中は能力の低い身体しかもっていない
野口飛行士は、人間の能力について洗面所の蛇口を例にユニークな視点を話してくれた。「私の親は(高齢者で)洗面所の蛇口をうまく回せない。だから回しやすいようにレバーをつけた」。人間の何らかの機能が損なわれたら、それを補うような機能を機械につければいい。一方、健康体である宇宙飛行士も「船外活動で蛇口を回すことはめちゃくちゃ大変で、ほぼ不可能。私も船外活動中は能力が低い身体しかもっていないことになる」(野口さん)。だからISSの船外装置は蛇口でなく(小回りが利きにくい手袋でも)つかめるレバーのような仕組みに作り替えるのだと。

障がいとは人間側の問題というよりは、状況や環境によって変わってくるもの。宇宙という極限環境での滞在は、まだまだ知識化・言語化されていない経験の宝庫。学ぶべき点が大いにありそうだ。
人の価値は能力の有無だけで決まるのか
会見に続いて行われたシンポジウムでは、オリンピックアスリート、宇宙飛行士、障がいの当事者たちから発表が行われ、当事者にしか語れない経験や葛藤が言語化された。
例えば女子バレーボール元オリンピック日本代表の田中祥子さんは20年以上前の厳しい体験をまるで昨日のことのように詳細に語った。シドニー五輪への出場権を得るための2000年の世界最終予選、対クロアチア戦。あと4点でオリンピックに行けるという状況から逆転された。超満員の体育館の観客の「今日、オリンピック出場を決める」という期待が一転、落胆に。その後の記者会見も含めて「忘れられない」と田中さんは語る。バッシングの渦中で、責任を感じ続けたという田中さんの言葉から「勝利至上主義」に苦しむトップアスリートの苦悩が伝わってきた。

「次のオリンピックに出ることでしか取り戻せない」と次の五輪に出場することを決意。新監督とキャプテンの元、2004年に五輪の出場権を得た時は「嬉しいというよりほっとした」。2回のオリンピックに出場、引退後は五輪を超えるやりがいを見出すことがなかなかできなかったと語る。「アスリートは職人と同じ。練習して技術を身に付けて発揮するが、その時期は限られている」。アメリカでは現役時代に何十億と稼ぐ選手もいる。日米のアスリート格差も指摘した。
そもそも、熊谷准教授が当事者研究でライフコース(人生の道筋)を考え始めたきっかけは、2016年に神奈川県相模原市で起きた痛ましい事件だったと語る。障がいをもつ仲間が命を奪われた。犯人は「人の価値は能力で決まる」という優生思想を殺害の動機としてのべた。「何としてもこの考え方をひっくり返さなくては」熊谷准教授は決意する。
障がいをもつ人は二つの主張をする。一つは「社会的な障壁を取り除くことなどで、最大限の能力を発揮できる社会を作るべき」。もう一つが「人の価値は能力の有無で決まるわけではない」。私たちは能力を発揮することを良しとする価値観に流されがちだが、それでいいのか。誰でも年をとれば能力を失う。その時、人としての価値まで失うのだろうか。年をとってもなおインクルードされる(包含される)、誰も取り残されない社会を目指すべきではないだろうか。
二つの主張の葛藤を生きるのは障がい者だけではないと熊谷准教授は指摘する。トップアスリートは「勝たない自分に価値はない」というプレッシャーが常にあり、ある種の優勢思想の最前線で戦っている人たちかもしれない。弱音をはきにくい環境にいるが、能力発揮という目標を譲るわけにもいかない。このせめぎ合いにいるアスリートたちから学べることがあるのではないか、と。
私のことは私にもわからない

そもそも当事者研究は発達障がいや精神障がいの方たちの研究からスタートしている。自閉症スペクトラムの当事者として活動し、2012年から東大先端研で研究員として働くのが綾屋紗月特任講師だ。
綾屋氏は「マイノリティは色々ある」と言う。自身は話したり聞いたりすることがうまくできないが、二足歩行ができるという点ではマジョリティに属する。宇宙飛行士やトップアスリートは職業経験のマイノリティ性があるし、家庭環境のマイノリティ性もあるだろう。様々な軸が考えられるが、苦労する点としては他者と苦労の経験を分かちづらい点。
自分自身の経験をもとに、綾屋氏は「人とのつながり」の困難さを3段階に分けて説明した。第1段階は自分のマイノリティ性を知らず、多数派の中で過剰適応していた時代。自分がどういう存在か見つけられない、自分が感じていることを周囲の人に「よくわからない」と受け取ってもらえない。多数派の中心的な人から「みんな大変なのは同じだから頑張ろう」と声をかけてもらっても、こんなに頑張っているのにそれでもできない自分はだめ人間かと落ち込んでしまう。
孤立した少数派に必要なのは仲間との分かち合いの段階。それが第2段階だ。発達障がい者のコミュニティで、似たような経験をもつ人たちが自分の像を固めていく。だが、コミュニティ内でも互いに比較し嫉妬が生まれ始める。「高学歴だからいいわよね」等々。そこで必要になるのが当事者研究だと綾屋氏はいう。「私のことは私にもわからない、痛みは分かち合えるという前提にたち、等身大の自分たちのニーズを明確化し環境を変えていくことが必要」だと。
「最初は仲間の中で、自分が何者なのかを周囲と作り上げて共有していく。自分に対する新しい実験を生活の中で行う。変えられるところを発見できれば面白いが、変えられない部分があったとしても、丁寧に分析をして社会のデザインを変える資源になれば」
埋めようのない喪失感を抱えて

パネルディスカッションで綾屋氏からこんな問いがあった。「障がいや病気を経た仲間たちは人生が全部うまくいかない気持ちを抱えながら仲間と繋がり、ギリギリのところを生きている人が多い。宇宙飛行士やオリンピック選手らは一見華々しく見えるが、命を削る想いで勝負の世界を生き、弱みを出してはいけない規範の中にいるのではと想像する。ギリギリのところで戦うという点で繋がれると思うが、そんなエピソードを聞かせてもらえたら」。この問いに対し、野口飛行士は「あまりこの話はしないのだが」と前置きをした上で語り始めた。
「私にとって宇宙飛行士を続けてきた最大の意味は(スペースシャトル)『コロンビア号事故』。7名の仲間を失って、埋めようのない喪失感を抱いた。自分はその時新人で、宇宙に行く直前だった。もしあの事故がなければ1回目の宇宙飛行で『良かった』と満足して、宇宙飛行士をやめていたかもしれない。(僕が)帰還することにこだわるのは、帰還できなかった7名の仲間たちがいるから」
元宇宙飛行士の山崎直子氏は「転機」を問われて宇宙から地球に戻った時をあげた。「宇宙に行く前に万が一に備えて遺書を書く。自分がいなくなったあとも家族の人生が回るように。(帰還後の)人生は、生かされている気がします」と。
東大・先端研の神崎亮平所長は「コロナ禍という未曽有の逆境は言葉や知識が追い付かない様々な困難を与えている。困難を表す言葉が存在せず、口にすると誤解や偏見がもたれることもある。誰も取り残されないインクルーシブな社会の実現に向けた当事者研究を全力で応援し、社会への貢献の一つの形にしたい」と力説した。
宇宙飛行士も障がいを抱える人も、アスリートもみなで取り組む当事者研究が、様々な生きづらさを抱える人々、そして私たち自身の長い人生の生き方にどんな光をあててくれるのか、今後に大きな期待をもって注目していきたい。
- ※
本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。